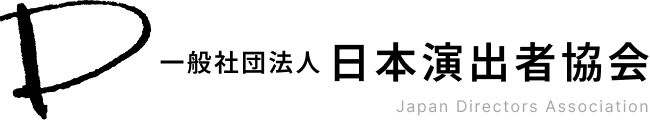# WEBマガジン「D」
EMMA広報部「 D 」コラム 「 字幕と演劇 」

近頃、演劇の「 字幕 」に関心があります。
昨年演出をした際に「 英語字幕付き上演 」をおこない、舞台における字幕表示の面白さや難しさ、可能性を感じたことがきっかけです。その公演では、パネルを使って字幕を表示しました。プロセニアムアーチ下部の左右両側に黒いパネルを設置し、白い文字を出力する方法です。
公演当日は、俳優の発語に合わせてボタンを押して切り替えていただき、タイミングもばっちり。( 3千回だったか…? )パネルに表示される文字の大きさや明度も調整でき、真っ白から濃いグレーまで色の変更も自在だったので、暗転明けの薄暗いシーンではグレーを多めにして文字の明るさを抑えたりと、工夫してもらいました。
この公演の経験を通して、「 字幕 」ってそもそも何だろう?と興味が湧いたのです。
多くの人にとって一番馴染みのある字幕は、やはり映像の枠の中に表示されるものだと思います。洋画や海外ドラマを観るときには欠かせませんし、テレビのバラエティーやニュース番組、YouTubeの動画でもテロップが活用されています。
映画やドラマの場合は、他言語で交わされる会話を理解するために無くてはならないもの。ニュース番組では、話題の要約や注目すべきポイントが示されていて、内容を理解するための助けとなります。 バラエティーやYouTubeはもう少し自由で、番組の方向性や動画編集者の息遣いが透けて見えることもあります。不思議なのは、例えば画面の中の芸人が何かネタをやって、私自身はそれを面白いと思えなくても、良きタイミングで客観的なテロップ( 突っ込み )が入ったりすると、たちまち笑いが生まれることです。それは「 出演する芸人 」と「 動画作成者 」の共同作業を見ることによって、「 私 」の中に新たに価値が生み出される瞬間・・と言えるかもしれません。出演者、編集者、視聴者、どれが欠けても成立しない笑いです。
では、演劇の上演における字幕はどうでしょうか。
これまで、さまざまな舞台で実際に字幕を目にしてきました。多くは、海外招聘作品で、セリフの日本語訳が表示されるものでした。 舞台上に文字が出ると、私の場合は瞬時にそれを「 読もう 」「 理解しよう 」という意識が芽生えます。文字の分量が多かったり、俳優と字幕の距離が遠い場合、眼球の往復運動が始まります。自分は主に「 文字 」を読んでいて、俳優の存在はその補足説明のように感じてしまう時すらあります。字幕なしの観劇と比べると、目や脳の疲労度は桁違いです。また、演劇の現在性が損なわれる感覚もあります。
10年以上前に、ピーター・ブルック氏の『 THE SUIT 』や『 Battlefield 』を日本で観劇しました。その時は必要最低限の、非常に短い日本語字幕が添えられていて、基本的に「 俳優を見続ける 」ことができた記憶があります。
現在はあらゆる技術が発展し、字幕の表示方法も多岐に渡ります。スマートグラスでメガネの枠内に文字を表示する方法も、そろそろ演劇界で実装されるかもしれません。自身のスマホや透明なパネルに、リアルタイムで自動翻訳が表示され、複数の国の方が同時に同じ舞台を楽しめる未来もそう遠くないかもしれません
調べていると、バリアフリー演劇の実例も見つけました。舞台上の大きなスクリーンの前に俳優が立ち演技をするのですが、まるで漫画のように、発語者の周辺にセリフが書かれた吹き出しが現れるというものです。
以前、耳が一切聞こえない方に「 今までどのような舞台が良かったですか? 」と問うと、あるコンサートで、風船を腕に抱えながら鑑賞できたことがとても良かったという返答をもらいました。音の振動で風船が動き、音楽を感じることができた、と。
字幕上演の目標のひとつは、さまざまな方が一緒に舞台を楽しめる環境を作ること。
「 生の舞台 」を「 共に 」鑑賞しているという感覚を大事にしていきたいなと考えています。

EMMA