CLOUMN
広報部コラム『多文化共生と演劇』ニノキノコスター

筆者が住む東海地方は工業都市が多く、外国人労働者との共存は半世紀に及ぶ課題であった。そこで20年前から演劇創作を通して日本人と外国人の交流を計っているのが岐阜県可児市だ。こちらの「ダンス公演」に今年から関わらせて頂いているのだが、言語獲得時期による学びの困難が目立つ。例えば日本語が理解できず孤立し不登校やブラジル人学校に転校する子供。これは母国にて小学校まで卒業してから来日する子供に多い。同時に、両親は外国籍だが本人は日本生まれ日本育ち言語も日本語である少女はこう述べた。
「親が通訳役として自分を利用するのをやめてほしい」
言語がマイノリティであるだけで状況は困難となる。
その一方で「何年も日本に居るのに何で日本語覚えないの?」とアッサリ述べる来日数年目、複数大学での学士号を持つインドネシア人もいるのだから、自身が優秀である自覚を持たぬまま自己責任論に走る人は国籍問わず存在するのだ。価値観や能力の相違を認識することは国籍問わず考えなくてはならないことである。
これは、ジェンダーについて学び演劇公演を行う大学の演習だとより顕著だ。私が関わり始めて以降は国籍・言語ともに日本人100%である。
今までは自認や嗜好がマイノリティ側である学生が多少存在していたのだが、「両親にはゲイであることを必ずカミングアウトすべき、育ててもらった恩があるから」とヘテロセクシャルが述べたり、「制服を変えてもらったことを誇るなんて我儘」とシスジェンダーが述べたり、幼さや経験を差し引いてもマジョリティである自覚が失われている。というか、無い。
推測だが、彼らは社会の被害者である自覚が少なからずある。ゆえに「日本国籍/日本語話者/男性/健常者/私立大学に通える家庭環境」であっても、その特権を認識できぬのだ。
ヒッタイトの粘土版(「最近の若いモンは」)のようだが、決してこれまでマジョリティがマイノリティのことを考えてきたとは言えない。しかして前者・後者共に当事者へのインタビューで構成されること、そこに想いを馳せること、創作というフィルターを通すことで観客に届けることを踏まえると、如何にバイアスが強固になっているのか、よりダイバーシティが前提となっている時代に何故、などと思う。
これからまだ数年は関わり続けていくと思うが、我々は、当事者が抱えている困難を、安心して吐いてもらう先にしかなれない。それを作品を通じて知ってもらうしかできない。けれども。それでも。
ニノキノコスター

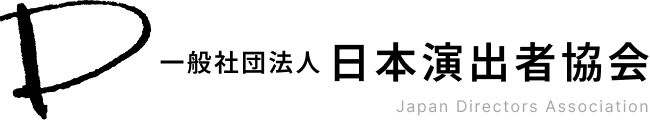


.jpg)